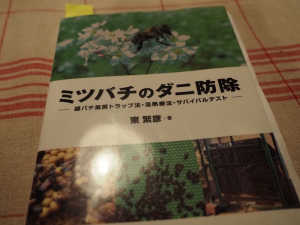自然巣だとダニが増えない説の検証①
投稿日:9/25 16:35
今年からセイヨウミツバチも飼っているんですが、生産性度外視で「自然巣だとダニが増えにくい説」が本当かどうか検証しています。
この説は、か式の岩波金太郎氏の「はじめての自然養蜂」や「ミツバチのダニ防除」の東繁彦氏のコラム(懐疑的ではある)で紹介されていて、私もかなり半信半疑なんですが、当地埼玉ではアピスタン耐性がすでにかなり高レベルで獲得されていて、最近はアピバール耐性も噂され、遅かれ早かれ新しいダニ対策が必要になるだろうとの考えのもと、検証してみることにしました。
検証開始から今まで、ダニ剤や有機酸、精油等は使ってません。オス蜂児切りは交尾オス用のA1以外は結構まじめにやりました。巣箱は全部自作で、標準サイズとか式、素材は杉赤身です。
種蜂導入は4月24日、3枚群2群(AとBとする)を購入しました。購入元では、昨年かなり耐性ダニ被害がひどく、2月に予約していたものが二カ月遅れの納品となりました。
5月~6月中旬の流蜜期に、Aは自然巣12枚、Bは自然巣6枚まで増えました。この時点で既存の巣礎枠はすべて廃棄し、完全に自然巣だけの状態になりました。自然巣への変換初期に想像以上にオス巣房だけが作られ続けたのはビビりましたが、後半は落ち着きました。AとBの差については、個体差かな?と思ってました。


6月23日にAをA1、K1、K2(Kはか式のK)に3分割し、BをB1、B2に2分割しました。K1とK2はそのまま変性王台で新女王を作り、7月15日にどちらも産卵確認、B2には購入した新女王を入れこの時点で5群となりました。

さらに7月下旬にA1を2分割しA1、A2に、B1とB2からB3を作り、計7群となりました。この時点で全群を腹側撮影法で検査したところ、A1、A2、K1、K2は0パーセント台、B1、B2、B3は2~3%でした。この時B2の女王をA2に移しました。またB1の女王はB3に移し、B1、B2は無王群となりました。

B3を作った段階で、B系統の群れのダニ率は結構高く2後半~3%だったため、B1、B2には、無王化から25日ほど経ち、有蓋蜂児が全くなく且つ新女王が産卵開始したくらいのタイミングで、か式群から借りてきた幼虫枠をトラップとして2枚づつ入れました。その結果、両群から大量のダニを捕獲することに成功。これを見て、自然巣ダニ減る説は眉唾かもしれないと心が折れそうになってました(笑)
ちなみにここで確信したのが、Bの元群は最初からダニが多かったから流蜜期の伸びが悪かったのだ!ということ。


B1、B2は各群とも5、6000匹くらいの群れだったと思いますが、各群から150~200匹ほどダニが取れました。蜂児が全部羽化するまでのタイムラグを考えても、腹側撮影法の数値はおおむね正確だったようです。
3パーセントといえども、こうしてみるとえげつないですねw
それから約一か月経ち、9月21日に全群でダニ検査をしました。





結果、A1、A2、B1、B2、K1、K2の順で、寄生率は1%以下、1%、1%、1%、3%、2%となりました。B3は事故で女王喪失中のため見てません。
興味深いのがA1で、この群は種蜂購入時から同じ女王で、オス蜂児トラップは5月~6月にそれなりにしましたが、7月からは交尾成功率上昇目的で半分くらいのオスを羽化させた群れでもあります。それでも1%以下に抑えられているのはすごいなと。おそらくなにかしらのダニ抑制要因を持っている系統と思われます。全群がこの群れだったら無農薬で全然やっていけそうです。
逆に、K1は3%、これはちょっとやばめな数値な気がします。埼玉ではたぶん後3サイクルくらいはダニ世代の回転があるはずで、世代増加係数を1.6としても、最大12%くらいに増えてしまうのではないかと思っています。もともとはA1と同時にAから分けだした群れなのに、女王の性質が違うとここまでダニ率に違いが出るようです。
9月下旬で3%というのが、金太郎さんの言う「自然巣ならダニが増えにくい」っていう説の安全域の範疇にあるのかはわかりませんが、これで冬に突入するのはどうなんだろうと思います。ちょっと怖い気がします。経験者の意見が聞きたいところ。正直、いまさらアピバールは使わないけど、乳酸ぐらいは使った方がいいかなとも思ってます。
そもそも金太郎さんの本のセイヨウミツバチのダニに関しての章はちょっと、ん?と思うとこがあったんですよね。まず、ダニ検査の光景として使われてる写真が、か式の連結枠で、これ、他の慣行養蜂家から標準ラ式群を買ってか式に移し替える段階の、か式飼育としてはごく初期段階のものなのでは?と思ったこと。さらに「オス蜂児のダニ寄生率10%!ドヤ!!」ってとこ。それふつうに多くない?って思ったんです。そして、セイヨウミツバチをか式で何年継続して無農薬でできましたみたいなデータが載っていないのも気になってました。とにかく数年分のデータで出してくれ!ってもどかしく思ってます(笑)
でもこれは希望的観測なんですけど、無農薬で飼うことにより、ハチの嗅覚や免疫が上がり、3%以上にはダニが増えないっていうこともあったりするのかもしれないと思ったりもちょっとしてます。(文面から不安がにじみ出すぎww)
まあとにかく、3%の群れはおそらく乳酸を使って対処すると思います。このまま放置してみたい気もするけど、盗蜂からの全群崩壊みたいになったら洒落にならないので。
他の群れはこのまま放置してみます。
おまけ
この3%の群のダニの増え方を計算してみました。6月下旬に母群Aから分けだした段階で推定0.5%のダニがいたとすると、30/6000匹=0.5%から240匹/8000匹=3%になったとしてダニ1世代(20日とした)あたりの増加係数は(240/30)^ 1/4.5=1.59 となりました。これは「ミツバチのダニ防除」に書いてある1.45という数値に近いけど、それよりもちょっと多く、この増加係数を見る限り「自然巣ならダニは増えにくい」っていうのはめっちゃ嘘ですね。むしろちょっと増える(笑)