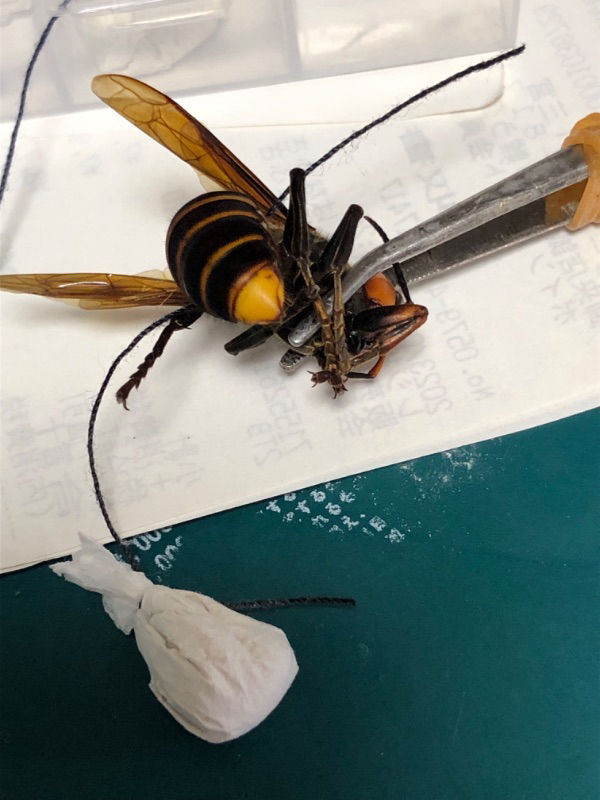継箱をしている際の、1段目の内検について
投稿日:2018/7/30 23:44
西洋ミツバチの養蜂をはじめたばかりの初心者です。
継箱をしている際(2段以上の状態)の内検について教えてください。
継箱をしている群の内検はどのように行っていますか?
①上段の巣箱を降ろして内検していますか?一番上の巣箱のみ内検していますか?
②季節によって、内検の頻度に違いが出ますか?
③1段目に隔王板をしていると、内検の方法に違いが出ますか?
教えて頂けるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いします。
隔王板を挟み下段で女王蜂に産卵させている間は上段に変性王台ができる可能性がある巣脾枠移動をしてない限り下段のみの内検を週1回行っています。
しかし流蜜期を過ぎて収穫の予定がなくなったら、ローヤルゼリー採取をしないのであれば隔王板は取り去るべきでいつまでも不必要にな物を入れて行動を制限すべきでは無いと考えます。
隔王板がない状態では、蜂数の増減に応じて上下段とも同じ巣脾枠数にし、女王蜂の産卵その他を観察する内検を行えばよく、花蜜流入量の変化に伴ってその場所が変化していきますから、分蜂可能性が無いと判断できる状態なら女王確認など必要最低限の巣脾枠を目視すればいいかと判断します。
内検開箱は、蜂たちにはストレス&迷惑であることは間違いなく実際に開箱した後の花蜜搬入量が半減する実証結果もあるほどですから無闇に実施することのないよう注意する必要がありますね(^^)