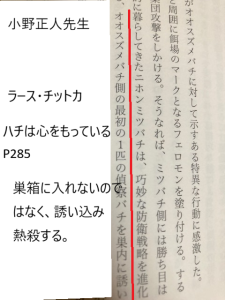鳥居金之丞備忘録 丸洞を10cm浮かしても微風であれば大きな障害にならない 2021年11月12日
投稿日:2021/11/12 16:55

******************************
例えば下の丸洞は縦型巣門が3本設けられているが、冬対策として巣門の数を2本にするとか1本にするとかは、微々たる問題であると結論する。
丸洞の中に10Wの電球を点灯して1週間温度測定を行った。
2日間は丸洞を床から5cm浮かせて、1日間は10cm浮かせて見たが、床下が微風である限り、大きな熱損失は無かった。
10cm浮かせた状態で(丸洞の底は無いので下面は外気に直接触れる事になる)、強い風を送り続けた場合には熱損失があるが、その場合の開口部は内径25cmの円なので、
面積はπアール二乗から0.049㎡となるが、縦型巣門1本の開口部は幅7mmで高さ80mmとして0.00056㎡なので無視しても構わない開口部と判断した。
この開口部は巣箱の下の位置に取り付けられている事は必要。
もし、巣箱の上の方に同程度の開口部(隙間)があれば、それは無視できない開口部と思う。

丸洞の高さ的には中間部辺りに10Wの電球を点灯した。
11月5日に点灯したり、点滅したり初期調整の後、第二期から常時点灯した状態を保った。
第二期は点灯して、丸洞の下は基台に乗せただけで浮かびあがせる事はしなかった。
この状態で気温とグラフ赤(丸洞の上の部分の温度)との温度差は平均8.7℃であり、その後
乱暴にも丸洞全体を基台から5cm、その後10cm浮かび上がらせて続行したが、浮かび上がった事で熱損失が顕著に見られたとは思わない。
浮かばせても基部の上に直接に載せでも大して変わらないと言う事が言える。
但し第五期のように丸洞を浮かばせた状態で1m離れた場所から扇風機を弱で掛けっぱなした場合にはそれなりの影響は見られた。
現実問題としてはこのような非常識な置き方はしないだろうから、地面・基台などに設置した場合には常識的な風よけ囲いをすれば熱損失を気にする事はないと思う。
よくあるケースでビールのケースの上に巣箱を置いて、底板を夏モードで抜いた状態で冬を越す事は誰しもしないと思うが、その状態が第五期と同様の結果になるのではなかろうかと予想される。

下のグラフは上のグラフに、紫色の温度差を加えたもの。
これは外気温を常時零度とか同じ温度と見立てて温度差を表示した。
傾向としては外気温の逆さまになっている。
昼の気温の高い時間帯では外気温より3℃から5℃位高いが、夜間から早朝の冷え込み時間帯には外気温より10℃程高い状態になっている。
これは10Wの電球を内部に入れた場合であり、実際の巣箱の中の日本みつばちが発熱している温度が何Wに相当するかは、分からない。
強引な仮定として10W=1000匹の働き蜂と語呂合わせをしてみてはいる。

以下は実際に実験で使ったもの。