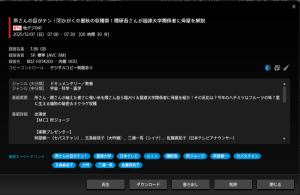三角積み木で巣箱内暖房効率up(アップ)
投稿日:2024/3/14 15:02
これは対流が激しくなる、つまり、巣箱内(育児域)と外部の気温差が大きくなる冬場に特に有効な気流制御による巣箱内環境改善かと思ってます。。単なる思い付きですが、、

考え方は簡単で、冬場は下降流を三角で跳ね上げ、底の冷たい空気に触れることなく、再び熱源である育児域(若しくは蜂球方面)に供給して、対流を全体的に小さくして保温効率を高め様と。
逆に夏場は下降流を巣門に誘導して排出することで、巣箱内を負圧にし外気を取り入れることで内部の熱を外に逃がす。尤も気温差が小さくなると対流自体が弱まるので、効果は冬場に比べれば弱くはなります。
まぁ、考え方は簡単ですが、実際の三角の寸法や置く位置なんかは条件に対してどの辺が最適か試行錯誤が必要かと思います。気流の可視化みたいな難しいことより、気流はイメージして、数値は温度を測定することで、セッティングを煮詰めていけば良いと思います、三角の大きさとか角度とか位置とか。
3月じゃないですね、12月に思い付くべきでした。。